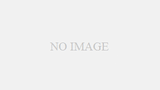国が打ち出した第3次国土形成計画。その中で10万人規模で「地域生活圏」の形成を打ち出し、その推進主体としてローカルマネジメント法人(地域運営法人)の創出を掲げた。
地域生活圏とは、通勤・通学など日常的な行動がほぼ完結した圏域で10万人規模を目安としている。自動運転、遠隔医療などデジタル技術を活かしつつ様々な生活サービスを提供する構想でのこと。
当計画では、民間の力を生かした推進体制の構築をはかっている。計画内では、会津若松市の協議機関、米子・境港市のローカルエナジー、三豊市の定額乗り放題のデマンド交通(暮らしの交通)、宮古市などが好事例として紹介されている。
宮古市は、国交省が参考にしたドイツのシュタットベルケをモチーフに、宮古版シュタットベルケとして、太陽光発電とその売電事業に取り組む民間会社に出資した。シュタットベルケは、地域ごとに自治体が出資して設けた公益事業体であり、電気・ガス・水道・交通など公共性のあるサービスを一体で提供するものであり、電力などで得た収益で全体の採算をとる仕組み。
日本は事業ごとに別々に運営され、法規制もあるなど、とにかく縦割りで、それを緩和しないと統合は難しいのではないかと記事はまとめている。
私としては、自治体が出資するにしても、いわゆる天下り法人にするのではなく、民間イズムで、それこそ労働者協同組合など新しい法人形態で運営するのも地域密着感が増して、よいのではないかと考えます。