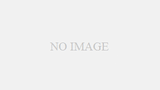地域ルールを良いことも悪いことも明文化する「集落の教科書」が広がり始めた、移住者とのトラブル防止が目的で、作成過程の話し合いは時代にそぐわないルールを見直す場になる
という9月14日の日経新聞記事
ルールはすべて明示する、自治会費から香典返しのやり方まで
ルールをどの程度守ればよいかは濃淡がある。現実に合わないなら話し合って見直す柔軟さも必要
話し合いには、役員のほか、女性や若者など多様なメンバーが参加し、発言しやすい雰囲気をつくる
話し合いには助言者も必要
このような教科書をつくった地域には2つの共通点がある
①人口減少への危機感
②定期的に話し合う機会
話し合いの基盤がなくなったのは、自治体の集落行政にも一因がある。住民に話を聞く場を設けても、結局行政側がまとめてしまうから
住民が少しずつでも変化を実行できるという期待感をもつこと、自治の力を回復することが集落の存続につながるとまとめられている。
紹介されていたのは、NPO法人テダス事務局長田畑昇悟氏