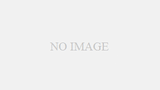ビジネスを生む「地元ぐらし」のススメ
とっても良い本でした。事例が豊富だし、アイディアも豊富、まちづくりに関心のある人にとっては、大いに参考になる本だと思いますし、相当刺激にもなります。
筆者がお3方とも建築分野ご出身ということで、多少建築方面の記載多めですが、ノウハウもたっぷりだし、収支が載っているのも参考になりますね
本の構成
1章 地元ぐらしのススメ
2章 地元ぐらし型まちづくりの仕組み
3章 地元ぐらし型ビジネスのハウツー
以下、章ごとに感想をまとめていきたいと思います。
1章 地元ぐらしのススメ
地元ぐらし型まちづくり
地元ぐらし型まちづくりとは?という項で、地元の課題解決がビジネスに直結とありながらも、全員を満足させなくてよい、でも地元にビジネスが生まれるというのはとてもよいと思いました。
特に従来型のまちづくりとの対比がいいです。誰に満足してもらうかは「全員」ではなく「共感者」、そしてかかわり方は「受動的」ではなく「主体的」に。
そういえば、この本の中には補助金の話はほぼ出てきません(紹介事例の中に活用している例はありますが)
地元のかかりつけ医になる
まずは気軽に行きやすい環境づくりを心掛け、人が集う仕組みをつくることが大事であり、専門職が営業をする場ではないとする。とにかく「行きやすさ」を優先する、そうすれば、訪れた人はついでに相談を持ち掛けやすい。たまたま行く店の人が専門家であればふだん相談する機会のない専門家に対しても相談しやすい。結果として営業をしない姿勢が営業につながる。いってみれば「かかりつけ医」というのは的確な表現だなあと。そういえば「まちの保健室」というのもありますね。
セレンディピティと居合わせ
さまざまな例が載っていました。地域マーケット運営委員会、駄菓子屋、マルシェ、野菜の収穫、展示など。共感や連帯感が生まれる場づくりをすればよいとあります。共同で何かを作り上げるのっていいですよね。
関わりたいときだけ関われる仕組み
従来の町内会のような組織はしがらみが多いという指摘には納得するしかありません。一方、農園、マルシェ、認知症カフェなどテーマ型の集まりは、行きたい時だけ行けばいい。たまの訪問でも歓迎される、そんな場に、というのはすごく賛成です。
小さくビジネスをはじめる(スモールスタート)
時間、コストを絞るという形で例示がありました。期間限定(シェアスペースの利用)、時間限定(曜日限定のカフェ)などなど。
2章 地元ぐらし型まちづくりの仕組み
12の事例が紹介されています。
1 ヤギサワスペース(西東京)
駄菓子屋併設でデザイン業拡大 子どもの居場所
2 KARSUI(北海道)
曜日限定カフェで人・仕事を発掘
3 市民集団まちぐみ(八戸)
アート活動が中心市街地の活力
4 喫茶キャプテン(那珂川)
店舗の継業で建築再生
5 ミサキステイル(三浦)
職住のお試しで空き家活用 トライアルキッチンで創業支援など
6 快哉湯(台東)
銭湯活用を機に建物再生の輪
7 みんなの畑(西東京) たもんじ交流農園(墨田)
都市公園が新たな付加価値を コミュニケーションの場としての農園
8 古小烏公園といふくまち保育園(福岡市)
公園管理と保育園運営を連携
この考えとても好きです。実際幼稚園の横に公園があったりするところは多く、公園を事実上の園庭としてつかっているところも多いのだから、まとめて運営ってとてもいいと思います。
9 DIY STORE三鷹
マルシェは地域ビジネスの好機
マルシェの新たな可能性にも触れられており、これってどこでも活用可能なアイディアと感じました。個人的には自分のいるエリアも地価の高いエリアで高い家賃などがハンデ?と思ってたけど、三鷹でできるなら言い訳はできないな、と思い知らされました。
10 箱バル不動産(函館)
建築家と不動産、パン屋が連携
函館という歴史ある街の力を思う存分生かそうとしているところが好きです。また、SNSで常に思いを発信することが大事ともあり、自分ももっとがんばらねばと思いますね。
11 スタジオ伝伝とHotel木ノ離(郡上)
観光客と住民を引き寄せる
12 PARK HOTEL犀(日南)
古民家再生で地域経済に循環 宮崎の小京都飫肥(日南市)にあるホテル。リノベだけではなく運営が大事というのはすごくよくわかります。また、行政とうまくやってる例だなとも思いました(多額の補助金も活用)
3章 地元ぐらし型ビジネスのハウツー
小さい収入を積み上げる、家賃を抑えるは至極ごもっともな話で、この本には収支実績が載っているのですが、家賃が非公表になっているケースが多いのも、おそらく相場よりかなり安く借りられていることがあるのでしょう。
不動産オーナーを応援者に、地元に覚悟を伝える、というのもよく分かる。ほか、どうやって広報していくかのアイディアも豊富に書かれていたり、普段から使ってもらう、なるべく巻き込む(頼る)というのもそうだよなあと思う。
まとめ
最初にも書きましたが、非常に示唆に富む本でした。多くの人に読んでもらいたい本です。