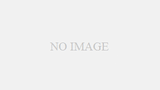この項では、以下のようなことが論じられていました。
自治会活動の持続可能性を高める必要性
担い手不足、加入率の低下が現状続いている。
その理由は複合的なものだが、社会全体の変化に起因するものがある。
(少子高齢化、ライフスタイルの変化、民間サービスの充実、SNSの普及による人と人とのつながり方の変化など)
また、役員の負担が重いから引き受け手がなかなかいないという問題はどこでも聞く話である。
その背景として、自治体の中に、ゴミステーションなど自治会の存在を前提に展開してきた施策がある。
以上はマイナス要因であるが、一方、デジタル化によって、自治体→自治会だった情報の流れが双方向性が期待できることから、住民自治を充実化させるプラスの側面もあわせ持っている
自治会の現状に対する自治体側の対応状況
この項で興味深かったのは、自治体の施策または自治会の独自の取組によって自治会の活動が変化したかについては、割とあるとの回答が得られていること。ただ大きいのは加入率の増ではなく、新たな活動の創出、地域の居場所との連携の創出などである。
事例としては、「なんでも相談カフェ」(宇都宮市)「交流イベント」(京都市)、「町内会受付センターの設置」(鹿児島市)、「地域の秋祭りの実施」(福岡市)
ほか、加入促進施策としては、自治会加入促進協定を不動産協会などと結ぶのも一定の効果があるとされている。(努力義務を課している例もある)
自治会の活動の持続可能性を向上させる取り組みを行う際の視点
加入案内を配布する方法は、各所で行われているが、ただそれだけでは不十分で、加入のメリットを丁寧に伝える努力が求められる。
ただ、実際、ちらし・パンフレット類の配布で実際に加入増につながった例もあるのであなどれない。
そのうえで、各団体の活動状況を幅広い年代の住民に詳細に伝えるためには紙媒体だけではなく、ホームページ等のデジタル媒体の活用についても触れられている。
また、行政協力義務が自治会を疲弊させていることに鑑み、その負担を減らすことも検討課題に挙がっている。ただなかなか進んでいないため、例えば逆に、有償ボランティアとすることも行われたりしている。