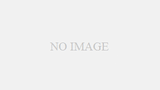総務省が2022年にまとめた地域コミュニティに関する研究会報告書に関するまとめ第3回めです。
今回のテーマは地域コミュニ的におけるさまざまな主体間の連携です
地域コミュニティの様々な主体間の連携を強化する必要性と現状
地域コミュニティ間のさまざまな主体間の連携を強化する必要性があるとされています。
例えば自治会のような地縁型組織と、NPOのような組織の連携・協働のことです。
この報告書では、主に防災分野・地域福祉分野を中心にまとめられています。
市町村には、地域の多様な主体が参画している協議会などのプラットフォームを積極的に構築していく役割を担うことが期待されるという提言が以前あったり、重層的支援体制整備事業について言及があり、自治会と行政とが連携をとった例として、地域課題について話し合う場を通じ潜在的ニーズの吸い上げを行った鳥羽市や自治会単位での連絡会を開催し、見守り活動の強化を図った鳥取県北栄町の例が紹介されています。
そして地域の居場所づくりについては、ボトムアップ型でさまざまな団体や企業との連携が進んでいる例が多く見られる(子ども食堂、コミュニティカフェなど)という指摘がなされています、
主体間の連携を通じて地域活動の持続可能性を高めようとする際に、自治会間の連携を強める方向性(B)と、地域活動の担い手を広げ、自治会、NPO,事業者との個別・限定的な連携協力を目指す方向性C)の2種類の方向性が存在し、さらに統合型地域コミュニティ組織の再構築(D)といった例もあるとされていること、さらに従来の自治会単体(A)とあわせると4つの方向性があるという整理から、各象限では、以下のような活動が行われているという指摘がありました。
A:役員の個人的スキルに依存している
B:デジタル化推進、防災力強化、小学校区以上の広域単位で実施することが効果的な活動
C:避難所運営や、学校との連携、子ども食堂などの運営など自治体主導も多い
D:防災や地域福祉の枠を越えた複合的事業
そして、これらの活動については、とにかく「見える化」、どこで何をやっているか、見せることが大切であるとまとめられています。
目的の明確化
自治会は趣旨・目的が広範で曖昧な点があることで、明確な目的意識を持った担い手の参加を促すことが難しくなっている側面があると考えられる。防災・地域福祉分野については住民の関心も高く、自治体としても、自治会が目的を明確にした活動を行えるよう支援することが重要になると指摘されています。
コーディネーターの役割
さまざまな主体の連携にはコーディネーターの存在も重要であるという指摘から、そのためには、まず自治体職員の中にも専門人材がいないと、自治体がコーディネーターの役割を果たすことは難しいため、例えば地域担当職員の仕組みを活用し、様々な団体の実態を把握し、関係者の間に入って適切に調整できる人材を育成することも重要と考えられること、また、コーディネーターは自治体職員以外でもよく、こうした人材の育成に努めるべきであるとまとめられています。
地域の居場所づくりを通じた多世代交流と主体間連携
主体間連携を促進する手法として、自治体が組織ありきで協議会等を設立すれば、会議や行事の開催が目的化するおそれがありますが、地域の居場所づくりなど、目的が明確なプロジェクトベースでの連携を促進することとすれば、自発的で貢献意識が高い団体、個人を集めることができ、実質的に地域活動を活性することが可能ではないか、という指摘があります。
まとめ
さらに全体のまとめとして、地域活動のデジタル化は、情報共有手段の効率化を図り、現役、若者の積極的な参加を促すことは、自治会の持続可能性の向上につながるとともに、見える化にも貢献し、主体間連携の強力なツールとなりうる点
目的が明確な活動において連携を進めることは、そうした活動に携わり、協力する住民が自治会の他の活動にも参画するきっかけを作ることになりうるとまとめあれています。